- トップ/
- こだわりケアワークブログ/
- 通所系の介護事業所における要件とは?~入浴介助加算について|
通所系の介護事業所における要件とは?~入浴介助加算について|
2024/01/30
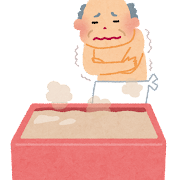
入浴は高齢者にとって生活の中の楽しみのひとつですが、介助の必要な高齢者にとって一般的な家庭の浴室は段差があったり、滑りやすいなど、危険が伴うこともあります。
自宅で安全に入浴するための方法を検討したり、通所系の介護事業所を利用して専門スタッフによる適切な介助で入浴することは、高齢者のQOLを維持することにもつながります。
2021年の介護報酬改定においては、機能訓練、自立支援の取り組みなどの観点から、自宅の浴室環境を整え、個別に入浴介助を行うことを評価する加算が設けられました。
今回は、通所系の介護事業所での「入浴介助加算」についてまとめます。
入浴介助加算については、次の記事でも詳細に解説をしています。併せてごらんください。
「入浴介助加算の通所介護における算定要件、個別の計画作成について」
目次
入浴介助加算とは
入浴介助加算とは、入浴のために適切な設備を整えて、入浴中の利用者の観察や介助を行った場合に算定できる加算で、2021年度の介護報酬改定において見直しが行われました。
改定以前は1種類だった入浴介助加算が入浴介助加算(Ⅰ)(Ⅱ)に分けられ、入浴介助加算(Ⅱ)では利用者が自宅で入浴するときの自立を支援することを目的に、利用者の居宅での入浴を前提として個別の入浴計画の作成と、その個別入浴計画に基づいたサービスの提供を評価する内容が盛りこまれました。
該当する介護サービスと単位数
入浴介助加算の対象となるサービスは通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーションです。
基本的には入浴介助加算(Ⅰ)40単位/日、入浴介助加算(Ⅱ)は55単位/日で、通所リハビリテーションで入浴介助加算(Ⅱ)を算定する場合には60単位/日となっています。
2021年度改定のポイント
改定以前の入浴介助加算と改定後の入浴介助加算(Ⅰ)が同じ内容で、新たに入浴介助加算(Ⅱ)が新設されたと考えることができます。
しかし改定前の入浴介助加算は50単位/日であったため、改定以前の入浴介助加算と同じ内容の入浴サービスを継続した場合は入浴介助加算(Ⅰ)を算定することとなり、10単位引き下げられたことになります。
入浴介助加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算は不可なため、入浴介助加算(Ⅱ)を算定できない場合は、改定前よりも実質減算となります。
入浴介助加算(Ⅰ)
入浴介助加算(Ⅰ)は基本的には2021年度の介護報酬改定以前の入浴介助加算と同じと考えて差し支えありません。
入浴の介助を適切に行うことができる人員や設備を有していて、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合に算定できます。
この場合の「観察」は、利用者の自立生活支援や日常生活動作能力の向上のための「見守り的援助」です。できるだけ利用者自身の力で入浴できるよう、必要に応じて介助や転倒予防のための声掛け、気分の確認などを行うことであり、その結果として身体に直接接触する介助を行わなかった場合でも加算の対象となります。
留意点
利用者の自立を支援するうえで最適と考えられる入浴方法がシャワー浴であっても、算定の対象となりますが、足浴などの部分浴や清拭では算定することはできません。
また通所介護計画に入浴の提供が位置付けられている場合でも、利用者側の事情によって入浴を実施しなかった場合には算定することができないので注意しましょう。

入浴介助加算(Ⅱ)
入浴介助加算(Ⅱ)は入浴介助加算(Ⅰ)の要件を満たしたうえで、利用者が居宅において自身で、または介助で入浴ができるようになることを目的としています。
利用者の居宅の浴室環境や利用者自身の状態に応じて、安全で尊厳を保持した入浴のためにはどのような介助や設備が適切かを考えることが必要です。
入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件をいくつかに分けて示します。
算定要件①
医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員、等(以下、医師等)が利用者の居宅を訪問し、利用者の状態を踏まえて浴室における利用者の動作や浴室の環境を評価します。
このときの評価のための訪問は、個別機能訓練加算で行う居宅訪問と合わせて実施することができます。
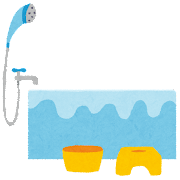
算定要件②
適切な介護技術に基づいて利用者の動作を踏まえ、利用者自身または家族や訪問介護員等の介助によって入浴を行うことが可能であると判断した場合、通所介護事業所に対してその旨を情報共有します。
利用者自身または家族や訪問介護員等の介助によって自宅の浴室で入浴をすることが困難と判断した場合には、訪問した医師等が介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携して、福祉用具のレンタルや購入、住宅改修など浴室の環境整備について助言を行います。
居宅を訪問して評価した人が通所介護事業所の従業員ではない場合には、書面などを活用して十分な情報共有を行うことが必要です。
加算要件③
機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種が共同して、居宅を訪問して評価した医師等と連携し、利用者の身体状況や浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成します。
加算要件④
③の入浴計画に基づき、個浴、その他の利用者の居宅の状況に近い環境で入浴介助を行います。
この場合の「個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境」とは、福祉用具などを活用し、利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したものとして差し支えないとされています。
個別入浴計画に基づく入浴介助とは
利用者の入浴にかかる自立を図る観点から「利用者が自身の身体機能のみを活用し行うことができる動作については、引き続き実施できるよう見守り援助を行う」「介助を行う必要がある動作については、利用者の状態に応じた身体介助を行う。」とされていますが、この「見守り的援助」と「利用者の状態に応じた身体介助」について、厚生労働省では「座位保持ができるかつ浴槽をまたぐ動作が難しい利用者が浴槽に出入りする場合」を想定して具体例を挙げています。
①介助者:シャワーチェア(座面の高さが浴槽の高さと同等のもの)、浴槽用手すり、浴槽内いすを準備する。
②利用者:シャワーチェアに座る。
③利用者:シャワーチェアから腰を浮かせ、浴槽の縁に腰掛ける。
介助者:利用者の足や手の動作の声掛けをする。必要に応じて、利用者の上半身や下肢を支える。
④利用者:足を浴槽に入れる。
介助者:利用者の身体を支え、足を片方ずつ浴槽に入れる動作の声掛けをする。必要に応じて利用者の上半身を支えたり、浴槽に足を入れるための持ち上げ動作を支える。
⑤利用者:ゆっくりと腰を落とし、浴槽内いすに腰掛けて湯船につかる。
介助者:声掛けをし、必要に応じて利用者の上半身を支える。
⑥利用者:浴槽用手すりにつかまって立つ。
介助者:必要に応じて利用者の上半身を支える。
⑦利用者:浴槽の縁に腰掛け、浴槽用手すりをつかみ、足を浴槽から出す。
介助者:必要に応じて浴槽台を利用し、利用者の上半身を支えたり、浴槽に足を入れるための持ち上げ動作を支える。
⑧利用者:浴槽の縁から腰を浮かせ、シャワーチェアに腰掛ける。
介助者:必要に応じて、利用者の上半身や下肢を支える。
⑨利用者:シャワーチェアから立ち上がる。
以上はあくまでも一例であり、入浴介助加算の算定にあたり必ず実施しなければならないものではありません。
個別入浴計画書
個別入浴計画書に必ず記載しなくてはならない事項は定められていませんが、算定要件の内容から「利用者本人の身体状況や疾患」「具体的な自宅の浴室の環境(手すりの有無や浴槽との段差など具体的な内容)」「利用者が居宅で入浴が可能かどうかの評価」「利用者自身、または家族の介助による入浴が困難な場合の助言」などの記載が必要と考えられます。
個別入浴計画は通所介護計画への記載が可能とされており、個別入浴計画書の様式は特別に用意されていません。
通所介護計画書の中に記載する場合、厚生労働省の模範様式(別紙様式3-4)では「利用者の居宅の環境」「健康状態」「ケアの上での医学的リスク、留意事項」欄などに必要な情報を記入することとされています。
計画の見直し期間は特に定められておらず、利用者の身体状況や居宅の浴室の環境に変化があった場合などには、再評価や計画の見直しが必要と考えられます。

留意点
浴室の環境を評価する専門職は上記の他、福祉用具専門相談員や機能訓練指導員に加えて地域包括支援センターの担当職員、福祉住環境コーディネーター2級以上の者などが想定されており、これらの専門職種は必ずしも事業所内の職員ではなくても、訪問リハビリテーション事業所や通所リハビリテーション事業所など、他の事業所と連携することで確保しても良いとされています。
またこの加算では個浴や居宅に近い環境で入浴を行うことが求められており、事業所の浴室が大浴槽であっても、居宅の手すりの位置にあわせて可動式の手すりを設置したり、浴槽の中に台やすのこなどを置いて浴槽の高さや深さを居宅の浴槽と合わせるなどの対応をして、居宅の浴室に近い環境が再現できれば算定可能とされています。
入浴介助を行う際は、利用者の状態などに配慮したうえで、自身で、または家族・訪問介護員等の介助によって安全に入浴ができるよう必要な介護技術の習得に努め、これを用いて行われることとされています。
自宅に浴室がない場合も、事業所の浴室で医師等が利用者の動作を評価し、自立した入浴を補助するための設備(福祉用具等)を備えて個別入浴計画を作成し、計画に沿って事業所で入浴介助を行うことで算定が可能です。
同一事業所において、入浴介助加算(Ⅰ)を算定する者と入浴介助加算(Ⅱ)を算定する者が混在しても差し支えないとされていますが、その場合には「介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」等は「加算Ⅱ」と記載させることとなっています。また「加算Ⅱ」と記載しても入浴介助加算(Ⅰ)の算定は可能です。
入浴介助加算のまとめ
入浴介助加算は2021年の介護報酬改定において見直しが行われ、入浴介助加算(Ⅰ)(Ⅱ)となりました。
入浴介助加算(Ⅰ)は改定前の入浴介助加算と同様の内容であり、入浴介助加算(Ⅱ)は利用者が居宅において自身で、または家族の介助によって入浴ができることを目的に新設されました。
専門職種が利用者の動作や居宅の浴室環境などを評価し、個別入浴計画を作成し、計画に沿った入浴介助を行うことで算定できます。
利用者が安全に自立した入浴を楽しめるよう、各専門職種が共同・連携して十分な情報共有を行い、入浴介助を実施しましょう。



