- トップ/
- こだわりケアワークブログ/
- 高齢者の食事介助の注意点・姿勢のポイントとは?食事介護の準備ガイド
高齢者の食事介助の注意点・姿勢のポイントとは?食事介護の準備ガイド
2025/10/28

高齢者にとって食事は、生命維持に必要な栄養摂取だけでなく、生活の楽しみや生きがいを感じるための重要な活動です。しかし、高齢者の食事は、加齢に伴う咀嚼力・嚥下力の低下により、誤嚥性肺炎や窒息といった命に関わるリスクが高まります。
食事介助の目的は、リスクを最小限に抑えながら、利用者が安全かつ快適に「口から食べる」を支援することです。本記事では、誤嚥を防ぐための正しい姿勢、嚥下機能に合わせた食事形態の工夫、適切な介助ペースと声かけなど、食事介助で大切なことや気をつけることを解説します。
レクの準備時間が増やせます。食事は温めるだけで完了
目次
食事介助における姿勢の注意点

誤嚥(ごえん)やむせを防ぎ、安全に食事を摂るための食事介助の基本とは、正しい姿勢を保つことです。姿勢が不適切だと、口元に食べ物を運ぶのが難しくなったり、食事中に疲れやすくなったりする原因にもなります。そこで、食事介助の注意点として姿勢維持の必要性について解説していきます。
誤嚥防止の重要ポイントは「正しい姿勢」
誤嚥や窒息を防ぐためには、正しい姿勢の保持が最重要ポイントです。椅子やテーブルの高さ、頭や首の角度を適切に調整し、リラックスして飲み込みやすい環境を整えることが、安全な食事介助の基本となります。
また、誤嚥は、高齢者の死亡原因に多い誤嚥性肺炎を引き起こすリスクがあるため、正しい姿勢で食事介助を行うことが日々の健康を保つためにも重要です。
基本の食事介助姿勢(頸部前屈位)
安全に食べ物を飲み込みやすい姿勢は、顎が上がらない程度に軽く前かがみになる「軽度頸部前屈位」の姿勢です。この姿勢では、気道が適度に狭まり、食道への流れがスムーズになるため、食事介助の基本姿勢となります。
一方で、顎が上がった姿勢(頸部伸展位)は、気管が開きやすく、食べ物が気管に入り込む誤嚥のリスクが非常に高まります。誤嚥や窒息のリスクが大きく上昇するため、絶対に避けなければなりません。
また、介助者が立ったまま介助を行うと、利用者は介助者を見上げる姿勢になるため、顎が上がった状態になってしまいます。そこで、介助者は必ず利用者と同じ目線の高さになるよう、横に座って介助することが大切です。
座位・車椅子での食事介助姿勢
基本的に、自力で座れる方であれば、座位で食事を摂ることが、誤嚥などを防ぐ最も望ましい方法となります。適切な座位姿勢は以下の食事介助の注意点を参考にして、正しく座ってもらいましょう。
座位姿勢を整える際は、まず椅子に深く腰掛けることが大切です。背もたれに背中をつけることで、体幹を安定させることができます。次に、両足を床にしっかりつけ、足関節と膝関節が90度になるよう調整しましょう。もし足が床に届かない場合は、台や雑誌を置いて高さを調整してください。
テーブルの高さは、肘が90度程度に曲がる位置が適切です。また、骨盤の位置は後傾せずにまっすぐ保つよう意識しましょう。
車椅子に座って食事をする場合は、上記のポイントに加えて、いくつか注意すべき点があります。まず、フットレストから足を下ろし、床にしっかりつけることが重要です。骨盤が後傾して背中が丸くならないよう、クッションを使って姿勢を安定させましょう。
安全のため、車椅子のブレーキをしっかりかけることも忘れないでください。さらに、アームレストの高さを調整し、テーブルに近づけるようにすることで、より快適に食事をとることができます。
寝たきりなど座位が難しい方がベッド上で食事をする場合、安全性と快適性のバランスを考慮した姿勢調整が必要です。そこで、以下のベッド上での食事介助の注意点を意識して、安全に食事ができる姿勢を保ちましょう。
まず、背上げ角度はリクライニングを45〜80度程度に設定しましょう。ただし、この角度は身体状況に応じて調整する必要があります。頭部は枕やクッションでしっかり支え、首が後ろに反らないようにすることが大切です。
顎の位置は軽く引いた状態を保ち、少し前傾姿勢をとるようにしましょう。膝の位置については、軽く曲げた状態でクッションを膝下に置くと、姿勢が安定します。また、体幹が左右にずれないよう、クッションを使って固定することで、より安全で快適な食事姿勢を保ちましょう。
体幹が不安定な方の場合は、30度の傾斜のほうが誤嚥リスクが少ない場合があります。そのため、個人の状態に応じて、医療職と相談しながら最適な角度を見つけることが重要です。
また、食後すぐに横になると、胃食道逆流による誤嚥や窒息が起こるリスクが高まります。安全のために、食後は少なくとも30分〜1時間程度は、座位または上半身を起こした状態を保つことが必要です。
嚥下機能に合わせた食事形態の注意点

高齢者は、加齢などの影響により噛む力(咀嚼力)が弱くなり、飲み込む力(嚥下力)も低下していきます。そのため、やわらかくて噛みやすい食材を選ぶことが重要です。ここでは、個人の咀嚼・嚥下機能に合わせた食事の工夫や食事形態について解説していきます。
咀嚼・嚥下機能の低下に合わせた食事介助の工夫
加齢により噛む力や飲み込む力が低下している高齢者だからこそ、食べやすい形態の食事が必要です。特に、高齢者の咀嚼・嚥下能力には大きな個人差があります。そのため、一人ひとりの状態に合わせた食事形態を選ぶことが、安全で楽しい食事につながります。
また、加齢により噛む力(咀嚼力)と飲み込む力(嚥下力)が低下すると、以下のような変化が現れます。
- 歯の欠損や筋力低下により硬い食材が噛めない
- 唾液分泌量の減少によりパサつく食材が飲み込みにくい
- 嚥下反射の遅延により誤嚥リスクが上昇
- 食道の蠕動運動が弱まり食べ物が残りやすい
こうした変化に対応するためにも、やわらかくて噛みやすい食材を選び、必要に応じて食材を細かく刻んだり裏ごししたりする工夫が必要です。
パサパサした乾燥食に注意
加齢によって嚥下力が低下したり、唾液の分泌量が減ったりすることで、食べ物が飲み込みにくくなります。特に、次のようなパサパサした乾燥食は、誤嚥や窒息のリスクが高いため、提供するときには注意が必要です。
- パン、トースト、クラッカー
- 芋類(サツマイモ、じゃがいも)
- 焼き魚、ゆで卵
- クッキー、カステラ
ただし、個人の趣向や栄養バランスのため、乾燥食を避け続けることはできません。乾燥した食事への対処法としては、いくつかの工夫があります。
あんかけやソースをかけることで、食べ物に適度な水分を加えることができます。また、スープや牛乳に浸して食べやすくする方法も効果的です。マヨネーズやバターで和えることで、しっとりとした食感になり、飲み込みやすくなります。
さらに、水分の多い料理と一緒に提供することで、食事全体のバランスを整え、より安全で快適に食べることができます。十分な注意と効果的な対策・工夫の両方を行い、乾燥食を安全に食べられるように提供しましょう。
水分・とろみの活用
乾燥食とは反対に、水やお茶などの液体は飲み込みやすい食べ物です。しかし、液体は喉を通過するスピードが速すぎるため、むせやすかったり誤嚥しやすかったりといったリスクがあります。
そこで、飲み物や汁物には、片栗粉などでとろみをつけて、喉に流れる速さを遅くすることが重要です。スピードがゆっくりになることで、気管の蓋を閉じるまでの時間を確保でき、誤嚥のリスクを大きく軽減できます。
一方で、とろみをつけすぎると、逆にベタついて飲み込みにくくなり、窒息のリスクが上がります。そのため、以下のとろみの指標を参考に、個人の嚥下機能に応じた適切な濃度のとろみに調整しましょう。
とろみの3段階:
- 薄いとろみ:飲み物がゆっくり流れる程度
- 中間のとろみ:スプーンで傾けるとゆっくり落ちる程度
- 濃いとろみ:スプーンで持ち上がる程度
ムース食・ソフト食の活用
咀嚼力や嚥下力が低下している方には、「ムース食」や「ソフト食」といった介護食の提供も有効です。それぞれの介護食には、主に次のような特徴があります。
- ムース食:ミキサー食をゲル化剤で固めてムース状にしたもの
- ソフト食:形を残しつつやわらかく仕上げたもの
基本的には、ムース食のほうがより柔らかく飲み込みやすい食事形態のため、咀嚼力や嚥下力がかなり低下している場合にムース食を活用します。
ただ、こうした介護食は食材の形を保つのが難しいため、見栄えが悪くなり、食欲が減退する可能性もあります。そこで、見た目や食器の色合い、盛り付けなどを工夫して、美味しそうに見えるように見た目を良くすることが大切です。
レクの準備時間が増やせます。食事は温めるだけで完了
介助ペースと声かけ・時間管理のポイント

安全かつ快適な食事時間を提供するためには、高齢者の状態や食欲に合わせた適切な介助ペースと、コミュニケーションが非常に重要です。ここでは、実践的なテクニックとして、食事を運ぶペースや声掛けといった食事介助の注意点を解説します。
高齢者のペースを尊重した食事介助
食事介助は、高齢者のペースに合わせてゆっくりとしたスピードで進めることが基本です。急かしてしまうと、咀嚼や嚥下がおろそかになり、誤嚥や窒息の事故を招く恐れがあるためです。
そして、無理なく飲み込める一口の量は「ティースプーン1杯程度(約3〜5g)」が目安となります。一気にたくさんの量を口に入れないように気をつけましょう。
また、口の中に食べ物が残っている状態で新しい食べ物を運ぶのも危険です。介助者は、飲み込んだことを喉仏の動きなどできちんと確認してから、次の一口を口に運びましょう。
食事介助は、高齢者のペースに合わせて行いますが、食事時間が長すぎると食べるのに疲れてしまいます。その結果、食事への集中力の低下を招き、誤嚥のリスクが高まるため、長くても30〜40分程度を食事時間の目安とするようにしましょう。
食事量が少ない場合は、間食や高エネルギーの栄養補助食品を活用したり、食事の回数を増やしたりすることで、栄養摂取量を調整するようにしましょう。食事量が少ない場合は無理して食事時間を伸ばす必要はないので、時間よりも回数や内容に目を向けることが大切です。
食事介助時の声かけとコミュニケーション
食事介助中は、「よく噛んでね」「飲み込んでね」など、嚥下を促す声かけを行い、食事への集中を促すことが大切です。
また、食事前に献立を伝えたり、「良い香りだね」など声をかけたりすることは、これから食事をするという認識を持ってもらうために有効です。食欲を刺激するためにも重要なので、声掛けや目線を合わせるといったコミュニケーションをとりながら食事介助をしましょう。
ただし、口の中に食べ物が残っている(咀嚼・嚥下している)ときは、返答を促すような声かけをしないよう注意が必要です。口の中に食べ物がある状態で声を出そうとすると、声門が開き誤嚥しやすくなってしまいます。そのため、食べているときは一方的な声掛け、飲み込んだ後は会話を楽しむようなコミュニケーションを心がけましょう。
また、食事中の会話や声かけは、リラックスを促し、食事への関心を高める効果がある一方で、過度な声かけは注意を逸らしてしまいます。集中力の低下を招き、誤嚥や窒息のリスクを高めるため、声掛けに適切なタイミングを見計らうことも重要です。
誤嚥・窒息事故防止につながる食事介助のポイント
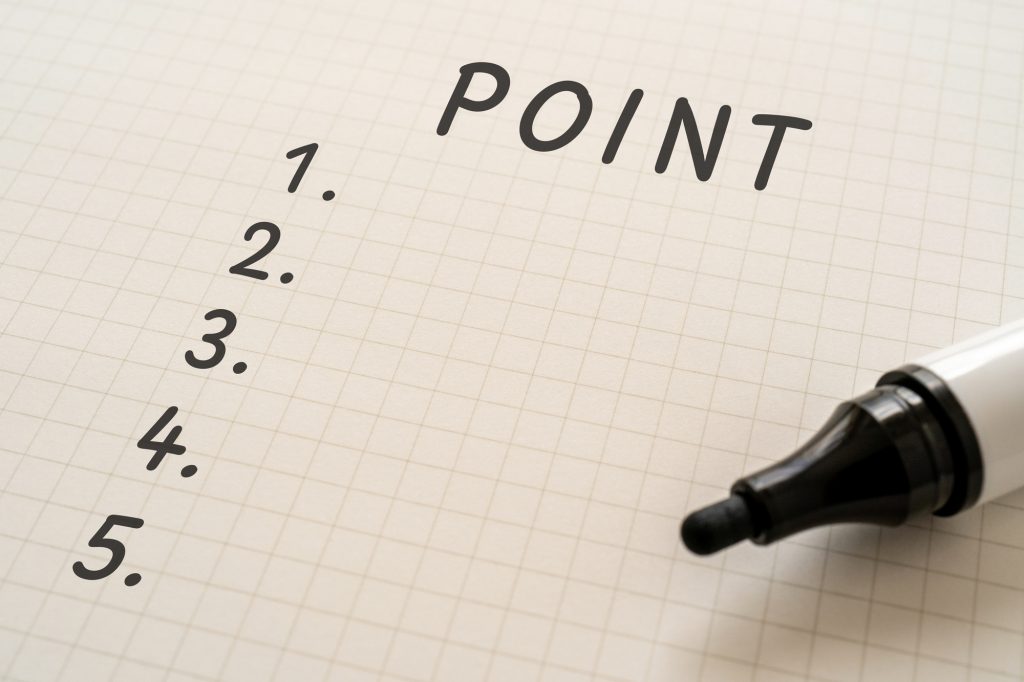
食事介助は、利用者が安全に食を楽しみ、栄養を摂取するために不可欠なケアです。特に高齢者においては、嚥下機能の低下から、誤嚥や窒息のリスクが伴うため、正しい方法と食事介助の注意点を知っておくことが重要です。そこで、誤嚥・窒息事故防止につながる食事介助のポイントについて解説していきます。
食事介助時の飲み込み確認方法
安全な食事介助を行うためには、次の一口を運ぶ前に、利用者が完全に嚥下したこと(飲み込みを終えたこと)を確認する必要があります。飲み込みの確認方法としては、喉仏(甲状軟骨)の上下の動きを見ることが有効です。喉仏が「ゴックン」と動く咽頭挙上を確認してから、次の一口を入れましょう。
また、飲み込んだ後も、口を開けてもらい、口の中にまだ食べ物が残っていないか(溜め込みがないか)を目視で確認することも必要です。口の中に食べ物が残っている状態で次々と食事を入れると、誤嚥や窒息の原因となります。特に、片側に麻痺がある利用者の場合、麻痺側に食事が残ってしまうことがあるため、特に注意が必要です。
もし以下のようなサインが見られた場合は、嚥下状況になにか問題が起きている可能性があります。
- 咽頭挙上(喉仏の動き)が見られない
- むせや咳き込みが頻繁に起こる
- 食後に声がガラガラになる(湿性嗄声)
- 呼吸が荒くなる
本人の様子を観察しつつ、深刻な状態だと判断したらすぐに食事を中止し、医療職の方に相談しましょう。
安全なスプーンの使い方
食事介助時のスプーンの使い方は、間違っていると誤嚥や窒息のリスクを高めてしまいます。そこで、食事介助の注意点として安全なスプーンの使い方を学んでおきましょう。
スプーンの口元への入れ方は、利用者の真正面かつ下方向から運びます。真正面から運ぶことで、利用者の顔がねじれるのを防ぎ、下方向から運ぶことで、顎を上げさせない姿勢(顎引き気味)で食事をしてもらえます。そして、スプーンは舌の中央あたりに置き、食べ物を落とします。
スプーンを口の奥まで入れすぎると、嘔吐反射が起こる危険があるため注意が必要です。高齢者が口を閉じたら、スプーンの動きが強い刺激とならないよう、水平にゆっくりと引き抜きましょう。
一方で、スプーンを斜め上方向に引き抜いたり、上顎を擦るように食べ物を届けたりする食事介助は、誤嚥や窒息などのリスクを上げてしまいます。慣れていないと上方向に引き抜いてしまうことが多いため、水平を意識してスプーンを引き抜きましょう。
食前・食後の口腔ケア徹底
食事介助と並んで重要なのが、食前・食後の口腔ケアです。口腔内を清潔に保つことが、誤嚥性肺炎の予防に直結します。食前・食後の口腔ケアには、主に次のような目的・効果と方法があります。
| タイミング | 目的・効果 | 口腔ケア方法 |
| 食前 | ● 口腔内の細菌を減らす:万が一誤嚥した際の誤嚥性肺炎の発症リスクを下げる
● 唾液の分泌を促す:味を感じやすくなり、食事を飲み込みやすくなる ● 口腔内を刺激:嚥下反射を活性化させる |
● 歯磨き、うがい
● 舌のクリーニング ● 嚥下体操(首や口の運動) ● 唾液腺マッサージ |
| 食後 | ● 食物残渣の除去:口腔内に残った食べ物をきれいに取り除く
● 細菌の繁殖を防ぐ:誤嚥性肺炎のリスクを大幅に低減 ● 口腔内環境の改善:次の食事への準備 |
● 歯磨き
● 義歯の清掃 ● うがい(できない場合は口腔内の拭き取り) |
食後の口腔ケアは丁寧に行うことが多い一方、食前の口腔ケアを行う方はそこまで多くありません。どちらの口腔ケアも重要ですので、忘れずに食前の口腔ケアにも力を入れて行いましょう。
レクの準備時間が増やせます。食事は温めるだけで完了
食事介助を支える「こだわりシェフ」

介護現場では、より安全で健康的な食事を提供する必要がある一方で、利用者さん一人ひとりの状態に合わせた食事を毎食用意するのは、大きな負担となります。そこで、専門家が開発した食事サービスを活用し、質の高い食事介助を効率よく実現することも有効です。株式会社シルバーライフでは、「こだわりシェフ」という施設向けに食材の配送サービスを提供していますので、当社の取り組みもぜひご参考ください。
こだわりシェフとは
「こだわりシェフ」は、障がい者施設や高齢者施設向けに提供される、完全調理済み冷凍パックの宅配サービスです。プロの料理人と管理栄養士が連携しメニューを開発しています。そのため、美味しさと栄養バランスに配慮した献立を提供でき、より利用者の好みや健康に寄り添った食事を提供できます。
また、こだわりシェフが配送した食材の調理や提供などに必要な機器やプレートの無料レンタルも実施しております。そのため、立ち上げたばかりの施設など、十分な機器やアイテムが整っていない施設でも、こだわりシェフをご利用いただけます。
専門家監修の品質
こだわりシェフは、プロの料理人と管理栄養士がタッグを組んで調理・監修を行っています。専門家が各方面から監修することで、次のようなメリットを提供しているのです。
- シェフ監修のメリット:献立と味付けを監修することで、食が進む濃い目の本格味付けが実現可能
- 管理栄養士監修のメリット:栄養バランスを考慮した献立を実現することで、塩分やカロリーを抑えながらも、満足感のある食事が可能
このように、異なるジャンルの専門家が監修することで、手軽に提供できるにもかかわらず、美味しさと健康に気遣った高品質の食事を利用者さんに提供できます。
関連記事:高齢者の食事で気をつけたい栄養バランスと冷凍食品の活用法
介護食の多様な対応
咀嚼・嚥下が難しい利用者様向けに、こだわりシェフでは冷凍タイプのムース食をオプションとしてご用意しております。嚥下機能が低下した利用者さんへも柔軟に対応可能です。
また、ムース食も他の食材と同様に解凍するだけで提供できます。同じタイミングで調理、提供が可能なため、食事の種類によって利用者さんを待たせることがありません。さらに、ムース食専門の人材を雇用する必要もないため、人件費のコストカット効果も期待できます。
豊富なメニュー
献立は、季節の素材を取り入れた飽きの来ないメニューに仕上がっています。和食、洋食、中華の豊富なバリエーションとなっており、同じメニューが続くことはないため、飽きずに食事を楽しんでいただけます。
そのため、長くこだわりシェフのサービスを利用されていても、利用者さんが飽きてしまうことはないでしょう。
「こだわりシェフ」が選ばれる理由
こだわりシェフは、サービスの開始以後さまざまな施設で利用いただいています。ここでは、どうしてこだわりシェフが選ばれているのか、その理由について解説していきます。
調理の手軽さ
こだわりシェフの食事は、冷凍パックで配送されます。調理は冷凍パックのままを湯せんするだけで完了します。商品到着から盛り付けまでの工程は、たったの2ステップで提供できるため、調理経験のない介護職員でも、手軽に美味しい食事を提供できます。
また、専門の調理師が常駐していない施設でも、介護スタッフだけで簡単に調理できるのも大きな強みです。人材不足に悩む施設でも導入しやすいため、幅広い施設で導入が進んでいます。
食品ロス対策に貢献
こだわりシェフが送付する冷凍パックは、長期保存が可能です。1人前パックなど小分けでの配送も行っているため、急な欠席などで必要な食数が変動した場合でも、無駄なく使いきることができます。
廃棄や再調理の必要がなく食品ロスを大幅に削減できるため、食事のコストを最大限活かすことが可能です。反対に、利用者さんが想定より増えた場合でも、保存していた食事を活用できるため、人数が変動しやすいデイサービスなどでも効果的に利用できます。
柔軟な注文体制
こだわりシェフは、1人前から注文できるサービスのため、小規模施設や食数が少ない施設でも利用しやすいのも強みの1つです。大口契約でムダにしてしまうことがないので、本当に必要な分量だけをお届けします。
また、全国の施設へ宅配が可能です。全国展開している施設でも同様のクオリティの食事を提供できるため、複数の施設を抱える法人からも高く支持されています。
安心安全の生産体制
こだわりシェフの食事は、衛生管理が徹底された国内の工場で、シェフが監修したメニューを作成しています。そして、調理後すぐに急速冷凍が行われるため、細菌が増殖する前に冷凍処理を完了できます。その結果、食中毒リスクの軽減にもつながります。
また、急速冷凍によって食事が劣化する前に冷凍してしまうため、出来立ての味を施設へ届けることが可能です。品質や美味しさ、衛生面など、あらゆる面を両立させた食事を提供できるよう、確かな生産体制を築いています。
関連記事:高齢者に適した冷凍介護食の選び方ガイド
まとめ
食事介助は、単に栄養を摂取させる行為ではなく、利用者の尊厳を守り、「食べる楽しみ」を提供する重要なケアです。本記事で紹介した正しい姿勢の保持、適切な一口量とスプーンの使い方、そして飲み込みの確実な確認を通して、安全な食事介助を目指しましょう。
また、利用者さん一人ひとりの状況に合わせた食事を提供する介護施設では、食事の準備や調理が大きな負担となっています。そこで、「こだわりシェフ」をはじめとする、調理済みの冷凍介護食の活用が進んでいます。
こだわりシェフでは、実際の調理・提供手順や、利用者の反応をご確認いただくため、無料サンプルの試食をご提供しております。導入をご検討の際は、ぜひお気軽に無料サンプルの請求をお申し込みください。
「人手不足」や「コスト」など、施設のお食事に関するお悩みはありませんか?
「調理スタッフの応募が全く来ない」
「急な欠勤が出るたびに、現場がパニックになる」
「委託費や食材費の値上げで、食事部門が赤字だ」
少子高齢化が進む今、専門職の採用難やコスト高騰は、どの施設様でも避けられない課題です。 「今のスタッフだけで、なんとか食事提供を維持しなければならない」 そんなギリギリの状況で戦っていませんか?
その課題は、「人のスキルに頼らない仕組み」を導入すれば解決します。 東証スタンダード上場企業が提供する「こだわりシェフ」は、まさにそのための切り札です。
採用不要: 「湯煎・解凍」だけなので、誰でも均一に提供可能。
コスト削減: 専門職の人件費や食材ロスをカットし、経営負担を軽減。
味も保証: プロの料理人と管理栄養士が監修した「確かな味」。
「本当に素人でも回せるの?」「コストに見合う味なの?」 その判断材料として、まずは無料サンプルで「調理の手軽さ」と「味」を体験してください。
既存会員の方以外なら、どなたでもお申し込みいただけます。
導入を強制することは一切ありません。「万が一の時の備え」として試しておくだけでも価値があります。
まずはリスクのない無料サンプルで、その「手軽さ」と「味」を体感してください。



