- トップ/
- こだわりケアワークブログ/
- 「施設の食事が合わない」は危険信号?健康リスクと家族ができること
「施設の食事が合わない」は危険信号?健康リスクと家族ができること
2025/10/17

「親が施設のごはんをおいしくないと言っている」「最近、食事を残すことが増えた」。
そんな話を聞くと、心配になりますよね。
高齢の方にとって食事は、栄養をとるためだけのものではなく、毎日の楽しみであり、心の支えでもあります。
だからこそ、食事への不満は単なる“好みの違い”ではなく、心や体の変化を知らせるサインであることも少なくありません。
この記事では、介護や栄養の専門家の視点から、「施設の食事が合わない」と感じる背景をさまざまな角度から見ていきます。
また、そのままにしておくと起こりやすい健康への影響についても、わかりやすく解説します。
さらに、ご家族が今日からできるサポート方法を、「すでに施設に入居している場合」と「これから施設を探す場合」に分けてご紹介します。
最後まで読んでいただければ、ご本人が再び“食べる喜び”を感じられるようになるためのヒントがきっと見つかるはずです。
スタッフが欠勤しても、少人数で食事提供を継続できます!
目次
なぜ施設の食事は合わないのか?考えられる5つの根本原因
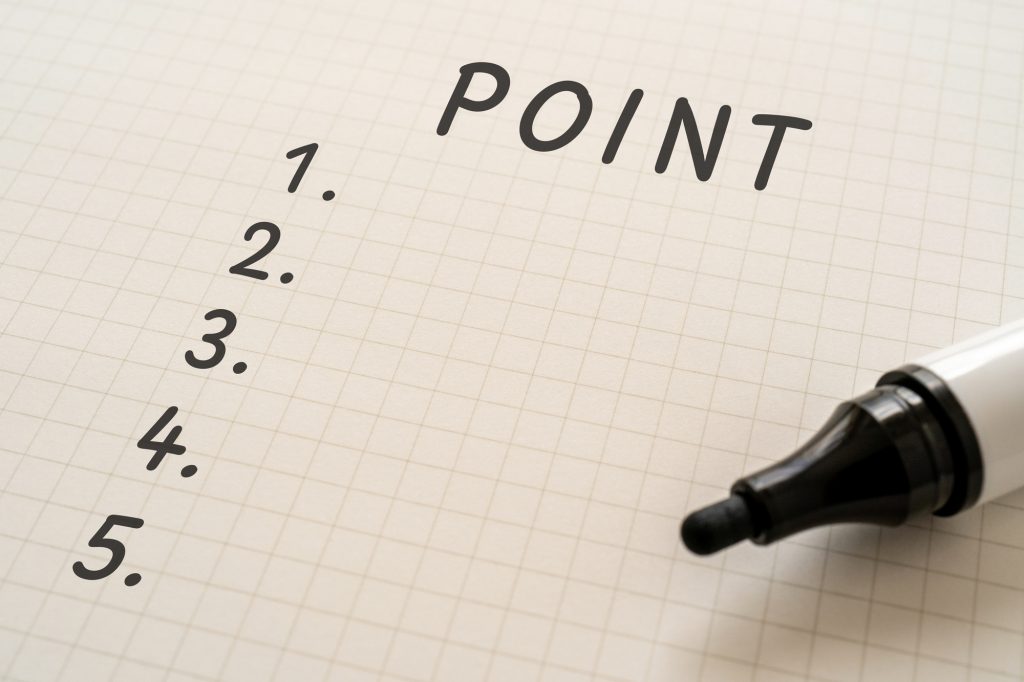
施設の食事が合わないと感じる背景には、単純な「味付けの問題」だけではなく、ご本人の身体的・心理的な変化や、施設運営上の制約など、複数の要因が複雑に絡み合っています。原因を正しく理解することが、適切な対策を立てるための第一歩です。
原因1:健康を優先した食事と個人の味覚のズレ
多くの施設では、入居者の健康を第一に考えた食事が提供されます。しかし、その健康への配慮が、個人の味覚とのギャップを生むことがあります。このズレは、
- 施設の医学的・栄養学的な配慮
- ご本人の加齢による生理的な変化
- 長年の食生活で形成された嗜好
という3つの要素が衝突することで生じます。
薄い味付け(減塩・減糖)
施設では、高血圧などの生活習慣病を予防・管理するため、栄養士が塩分やカロリーを厳密に計算した献立を作成します。
厚生労働省が定める75歳以上の食塩摂取目標量は男性で7.5g/日未満、女性で6.5g/日未満ですが、日本高血圧学会はさらに厳しい6.0g/日を推奨しており、多くの施設がこの基準に準じています 。家庭料理に慣れた方には、この健康的な味付けが物足りなく感じられることがあります。
加齢による味覚の変化
年齢を重ねると、味を感じる細胞「味蕾(みらい)」が減少し、特に塩味やうま味を感じにくくなる傾向があります 。研究によれば、74歳以上になると味蕾の数は若い頃の約35%まで減少するとの報告もあります 。
そのため、若い頃と同じ味付けでも薄く感じ、より濃い味を好むようになることがあります。施設の健康的な薄味は、この生理的な変化によって、さらに味気なく感じられてしまうのです。また、味蕾の新陳代謝に必要な亜鉛が、薬の副作用などで不足しがちなことも味覚低下の一因とされています 。
長年の食習慣との乖離
人は誰でも、生まれ育った地域や家庭環境で培われた「慣れ親しんだ味」を持っています。何十年にもわたる食習慣によって形成された味の好みは、簡単には変えられません。施設で提供される標準的な食事が、個人の食文化や好みに合わないと感じるのは自然なことです。
原因2:加齢に伴う身体的な変化
ご本人の身体に起きている変化が、食事を困難にしているケースも少なくありません。味付け以前に、「食べること」自体が難しくなっている可能性があります。
噛む力(咀嚼機能)の低下
歯を失ったり、入れ歯が合わなくなったり、顎の筋力が衰えたりすることで、硬いものや繊維質の多い野菜などが噛みづらくなります。この状態は「口腔機能低下症」と呼ばれ、40代から衰え始めるとも言われています 。
食べ物を十分に噛み砕けないと、食事に時間がかかり、疲れて食欲が落ちてしまいます。さらに、硬いものを避けることで栄養が偏り、全身の筋力低下につながる悪循環に陥る危険性があります 。
飲み込む力(嚥下機能)の低下
食べ物や水分を食道へ送り込む「嚥下機能」は、加齢とともに低下します 。飲み込む力が弱くなると、むせやすくなったり、食べ物が喉につかえる感覚が生まれたりします。嚥下障害の原因としては加齢のほか、脳卒中が約6割を占めるとされ、パーキンソン病などの疾患も関連します 。「誤嚥(ごえん)」への恐怖心から、食事そのものに消極的になってしまう方もいます。
安全に食事を楽しむためには、飲み込みやすさに配慮した食事の工夫が欠かせません。
嗅覚・視覚の衰え
食べ物の風味は、味覚だけでなく嗅覚によっても大きく左右されます。嗅覚が衰えると、料理の香りが分かりにくくなり、味が薄く感じられることがあります。また、白内障などにより視覚が変化すると、料理の彩りがくすんで見え、見た目から食欲を感じにくくなることもあります。
原因3:集団調理・施設運営ならではの制約
一度に大勢の食事を用意する施設ならではの、運営上の制約も食事の満足度に影響します。これは施設の怠慢ではなく、効率性や安全性を確保するために避けられない側面もあります。
食事が冷めている
施設内で調理する場合でも、調理完了から配膳、そして入居者が口にするまでには時間がかかります。特に、外部の給食会社(セントラルキッチン)で調理された食事を施設で再加熱して提供する場合、温かいはずの料理がぬるくなってしまうことがあります。料理の温度は、おいしさを左右する重要な要素です。
メニューの画一化
栄養バランスを保ちつつ、多くの人のアレルギーや嗜好に対応するため、どうしてもメニューが画一的になりがちです。毎日似たような献立が続くと、食事への期待感が薄れ、マンネリを感じてしまいます。
調理方法(施設内調理 vs. 外部委託)
食事の調理体制は、施設の食事の質を大きく左右する重要なポイントです。施設内の厨房で手作りする「施設内調理(直営)」では、できたての温かい食事を提供できるほか、利用者一人ひとりの好みや体調に合わせた対応もしやすいという利点があります。
一方で、外部の給食会社に委託する「外部委託型」では、衛生管理や栄養バランスがしっかりと保たれる反面、メニューの自由度が限られたり、利用者と調理者との距離が生まれやすいといった面もあります。
原因4:食事環境や心理的・社会的要因
食事の満足度は、料理そのものだけでなく、「誰と」「どこで」「どのような気持ちで」食べるかという環境や心理状態に大きく影響されます。
孤独感と環境の変化
長年家族と食卓を囲んできた方にとって、施設で一人、あるいは知らない人たちと食事をすることは、大きな孤独感につながります。慣れない環境での食事はストレスとなり、食欲不振を引き起こす一因となります。
食事の楽しみの喪失
自宅では「何を食べようか」と自分で決めたり、時には料理をしたりすることが生活の楽しみの一つでした。施設では食事が自動的に提供されるため、その「自己決定」の機会が失われます。受け身の食事が続くと、食事への関心自体が薄れてしまうことがあります。
活動量の低下
施設での生活は、自宅にいた頃よりも身体を動かす機会が減りがちです。活動量が低下すると消費エネルギーも減るため、お腹が空きにくくなり、決まった時間になっても食欲がわかないことがあります。
原因5:認知症による影響
認知症の症状が、食事の問題として現れることもあります。この場合、ご家族や介護スタッフは、その行動の裏にある認知症の特性を理解した上で対応する必要があります。
失認(食べ物の認識ができない)
認知症の症状の一つに「失認」があります。これは、目の前にあるものが何かを認識できなくなる症状です 。例えば、お箸を道具として認識できなくなったり、白いお皿に盛られた白いご飯を「食べ物」として認識できなかったりします。
アパシー(意欲の低下)
何事にも無関心・無気力になる「アパシー」も、認知症によく見られる症状です 。食事への意欲そのものが失われ、目の前に食事が並べられても食べ始めようとしないことがあります。これは、脳の視床下部の反応が鈍り、空腹を感じにくくなることも一因とされています 。
集中力の低下
認知症の方は、注意力が散漫になりやすい傾向があります。食堂のテレビの音や、周りの人の会話などが気になり、食事に集中できずに途中で食べるのをやめてしまうことがあります 。
妄想
「食事に毒が入っている」といった被害妄想により、食事を拒否することもあります。これは意地悪で言っているのではなく、ご本人にとっては真実であるため、否定せずに寄り添う姿勢が大切です。
関連記事:高齢者の適切な食事量は?栄養を補う方法やおすすめメニューも紹介
食事が合わないことで起こる3つの深刻なリスク

食事への不満を「ただのわがまま」や「好みの問題」と軽視してはいけません。食事が合わない状態が続くと、心身にさまざまな悪影響が及び、最終的には命に関わる事態に発展する危険性もあります。
リスク1:低栄養状態と身体機能の低下
食事量が減ることで、まず懸念されるのが「低栄養」です。高齢者の低栄養は、さまざまな健康問題を引き起こすドミノの最初の牌です。
低栄養のリスク
低栄養とは、体を動かすために必要なエネルギーやたんぱく質が不足した状態を指します 。世界の臨床栄養学会が提唱する診断基準「GLIM」では、意図しない体重減少、低BMI(70歳以上で20未満)、筋肉量減少などが指標とされています 。
低栄養状態になると、筋肉量が減少し、免疫力が低下します 。傷が治りにくくなったり、新型コロナウイルスを含む感染症にかかりやすくなったりと、体全体の抵抗力が弱まってしまいます 。
転倒・骨折のリスク増加
低栄養による筋力の低下は、ふらつきや転倒の直接的な原因となります。高齢者の骨折は、回復に時間がかかるだけでなく、そのまま寝たきりにつながるケースも少なくありません。
感染症への抵抗力低下
栄養状態が悪いと免疫機能が正常に働かず、風邪やインフルエンザ、肺炎などの感染症にかかりやすくなります。一度かかると重症化しやすいのも、高齢者の特徴です。
リスク2:QOL(生活の質)の低下と精神的な不調
毎日の食事が苦痛になると、生活全体の質が低下し、精神的な健康も損なわれていきます。
生きがいの喪失
多くの高齢者にとって、一日に3度の食事は生活リズムの中心であり、最大の楽しみです。その楽しみが奪われることは、日々の張り合いや生きがいを失うことにつながり、QOLを著しく低下させます。
ストレスと孤立感の増大
食事がおいしくない、食べづらいという状況は、毎日続く慢性的なストレスとなります。また、食事の時間が苦痛になることで食堂へ行くのをやめてしまい、他の入居者との交流が途絶え、社会的な孤立を深めてしまうこともあります。
うつやアパシーの発症
慢性的なストレスや楽しみの喪失は、うつ病やアパシー(無気力)の発症・悪化の引き金となることがあります。精神的に落ち込むとさらに食欲が低下し、負のスパイラルに陥ってしまいます。
リスク3:誤嚥性肺炎という命に関わる危険
特に噛む力や飲み込む力が低下している方にとって、合わない食事は「誤嚥性肺炎」という命に関わる病気のリスクを高めます。
誤嚥(ごえん)とは
誤嚥とは、食べ物や飲み物、唾液などが誤って気管に入ってしまう状態のことです 17。健康な人であれば、むせて気管から異物を排出できますが、高齢者はその反射機能も衰えていることが多いです 。
合わない食事がリスクを高める
硬くて噛みきれない食材や、水分が少なくパサパサした食べ物、そして注意が必要なのが口の中でまとまりにくいきざみ食です。これらは誤嚥を引き起こす原因となりやすい食品です 。噛む力が弱い方向けの「きざみ食」が、飲み込む力が弱い方にとっては、かえって誤嚥のリスクを高めるという、一見矛盾した状況が起こりうるのです。
誤嚥性肺炎
誤嚥した際に、口の中の細菌が食べ物などと一緒に肺に入り込むことで炎症を起こすのが誤嚥性肺炎です 。高齢者の肺炎の多くは誤嚥性肺炎が原因とされ、命を落とすことも少なくない危険な病気です。予防には、食事形態の工夫とともに、口の中を清潔に保つ口腔ケアが非常に重要になります。
スタッフが欠勤しても、少人数で食事提供を継続できます!
【入居後の方向け】施設の食事問題を解決する5つのステップ

すでに入居されているご家族の食事問題を解決するためには、段階を踏んで冷静に対応することが大切です。感情的に不満をぶつけるのではなく、建設的な対話を通じて解決策を探っていきましょう。
ステップ1:現状を正確に把握する
施設に相談する前に、まずはご家族自身が状況を客観的に把握することが重要です。具体的な情報があればあるほど、施設側も対応しやすくなります。
本人から具体的に話を聞く
「まずい」という言葉の裏にある、具体的な理由を探りましょう。
- 何が合わないのか(味付け、硬さ、温度など)
- 特定のメニューだけか、毎回のことか
- いつ頃からそう感じるようになったか
食事の様子を観察する
可能であれば、食事の時間に施設を訪問し、ご本人の様子を直接観察しましょう。
- 食べるのに時間がかかりすぎていないか
- むせたり、口からこぼしたりしていないか
- どのくらいの量を、何を残しているか
- 食事中の表情は楽しそうか、つらそうか
情報を記録する
聞いたことや観察したことを簡単なメモに残しておくと、施設スタッフに説明する際に役立ちます。「いつ」「何を」「どのように感じたか」を記録することで、話に具体性と客観性が生まれます。
ステップ2:施設スタッフへの効果的な相談・伝え方
集めた情報をもとに、施設スタッフへ相談します。伝え方一つで、相手の受け取り方やその後の対応が大きく変わります。
相談相手を間違えない
最初の相談窓口として適しているのは、施設のケアマネジャーや生活相談員、あるいはフロアの責任者(看護師長や介護リーダー)です。食事内容の専門的な相談であれば、管理栄養士に直接話を聞くのが最も効果的です。
感情的にならず、具体的に伝える
不満をぶつけるのではなく、「相談」という形で協力を求める姿勢が大切です。ステップ1で集めた具体的な情報を基に、冷静に状況を伝えましょう。
- 悪い伝え方の例:「母がここの食事はまずいと言っています。何とかしてください。」
- 良い伝え方の例:「母の食事の件でご相談です。最近、煮物が硬くて食べづらいようで残すことが増えました。また、全体的に味が薄く感じて食が進まない日もあるようです。食事の形態を少し軟らかくしたり、出汁の風味を足すような工夫は可能でしょうか?」
要望と質問をセットで伝える
「こうしてほしい」という要望だけでなく、「専門家の視点から見て、どのような対応が考えられますか?」と質問することで、施設側も提案をしやすくなります。
ステップ3:食事の個別対応を依頼する
多くの施設では、入居者一人ひとりの状態に合わせて、ある程度の個別対応が可能です。どのような選択肢があるかを知り、具体的に依頼しましょう。
食事形態の変更
噛む力や飲み込む力に合わせて、食事の形態を変更してもらうことは基本的な対応の一つです。介護食にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴と注意点があります。
| 食事形態 | 特徴 | こんな方におすすめ | 特に注意すべき点 |
| 常食(普通食) | 健康な方向けの一般的な食事 | 咀嚼・嚥下機能に問題がない方 | – |
| 軟菜食(ソフト食) | 歯茎や舌でつぶせる硬さに調理した食事。食材の形は残っていることが多い 。 | 噛む力は弱いが、飲み込む力はある方 | 調理に不向きな繊維質の多い食材がある 。 |
| きざみ食 | 食材を細かく刻んだ食事。刻む大きさは調整可能 。 | 噛む力が弱い方、口が開きにくい方 | 唾液が少ないと口の中でまとまりにくく、誤嚥のリスクがある 。あんかけなどでまとめる工夫が必要。 |
| ミキサー食 | 食材をミキサーにかけてなめらかなペースト状にした食事 。 | 噛む力も飲み込む力も弱い方 | 見た目から何かわからず食欲が低下することも。誤嚥防止のため、とろみ調整が必須 。 |
| ゼリー食・ムース食 | ミキサー食をゼラチンなどで固め、形を整えた食事 。 | 飲み込む力が特に弱い方、誤嚥リスクが高い方 | 見た目をおいしそうに工夫することで、食欲を維持する配慮が必要 。 |
農林水産省が定めた「スマイルケア食」のような統一基準を参考に、施設側と具体的な硬さについて相談するのも有効です 。
治療食への対応
医師から食事に関する指示(食事せん)が出ている場合、施設はそれに基づいた「治療食」を提供します。これは介護保険の「療養食加算」の対象となるサービスです 。
- 減塩食:心臓疾患や腎臓病の方向け(1日の塩分総量6.0g未満など)
- 糖尿病食:エネルギー(カロリー)や糖質を調整した食事
- 腎臓病食:たんぱく質や塩分、カリウムなどを制限した食事
ご本人の持病が悪化したり、新たな病気が見つかったりした場合は、速やかに主治医と施設に情報共有し、食事内容を見直してもらう必要があります。
味付けやメニューの工夫
大規模な施設では完全な個別対応は難しいですが、以下のような工夫に対応してくれる場合があります。
- 食卓に醤油やこしょうなどの調味料を置いてもらう(医師の許可が必要な場合あり)。
- 週に数回、メインのおかずを選べる「セレクト食」を導入している施設もある。
- アレルギーや強い苦手意識がある食材を、別のものに差し替えてもらう。
ステップ4:外部サービスを賢く利用する
施設内の対応だけでは解決が難しい場合、外部のサービスを組み合わせることで、食生活の満足度を高めることができます。
差し入れ(持ち込み)のルールとマナー
ご本人の好きなものを差し入れすることは、大きな喜びにつながります。ただし、他の入居者への配慮や食中毒防止のため、多くの施設ではルールが定められています。
- 必ず事前に施設に確認する:持ち込み可能なもの、禁止されているものを必ず確認しましょう。衛生管理の観点から、手作りの料理や開封済みの食品は禁止されていることが多いです。
- 本人の健康状態を最優先する:持病による食事制限(糖分、塩分など)やアレルギーの有無を考慮しましょう。お餅やこんにゃくゼリーなど、喉に詰まらせる危険性があるものは避けるべきです。
- おすすめの差し入れ:未開封で日持ちのする市販品が基本です。プリン、ゼリー、ヨーグルト、個包装のお菓子などは、多くの施設で受け入れられやすいでしょう。
高齢者向け配食サービスの活用
施設での食事に加えて、週に数回、外部の配食サービスを利用するのも一つの方法です。ご本人の好みに合ったサービスを選ぶことで、食事の楽しみが広がります。
選び方のポイント
- 療養食・介護食の対応:持病や身体状況に合わせた食事(減塩食、きざみ食など)に対応しているか 。
- 味付けと試食:多くのサービスでお試し利用が可能です。実際に食べてみて、ご本人が「おいしい」と感じるかどうかが最も重要です 。
- 注文・配送方法:毎日冷蔵で届くのか、冷凍でまとめて届くのかを確認しましょう。冷凍タイプは長期保存が可能で便利です 。
- 安否確認サービス:毎日手渡しで配達してくれるサービスの場合、配達員がご本人の様子を確認してくれる安否確認を兼ねていることもあります 。
ステップ5:最終手段としての転居(施設の住み替え)
あらゆる手段を尽くしても状況が改善されず、ご本人の健康状態に悪影響が出ている場合は、施設の変更(転居)も視野に入れる必要があります。ただし、転居はご本人にとって大きな環境変化となり、心身に負担をかけるため、慎重に検討すべき最終手段です。
- 転居を検討するケース:施設との話し合いが平行線に終わり、食事内容の改善が見込めない場合や、必要な医療的ケアに対応できなくなった場合などが挙げられます。
- 転居のプロセス:まずは現在の施設のケアマネジャーに相談し、協力関係を築きながら、退去を申し出る前に次の入居先を探し始めます。退去通知は一般的に1~3ヶ月前までに行う必要があり、契約書の確認が必須です。
- 転居に伴う負担:特に認知症の方の場合、環境の変化が症状の悪化を招くこともあります。転居は、他の選択肢がすべてなくなった場合の最後の手段と捉え、ご本人の心身への影響を最優先に考えましょう。
スタッフが欠勤しても、少人数で食事提供を継続できます!
【入居前の方向け】食事がおいしい施設を見極める4つのチェックポイント

これから施設を探す方は、入居後に後悔しないよう、「食事」を重要な選定基準の一つとして考えましょう。パンフレットの情報だけでなく、ご自身の目と舌で確かめることが大切です。
チェックポイント1:食事の提供体制を確認する
食事がどのように作られているかを知ることで、その施設の食事に対する姿勢が見えてきます。
- 施設内調理(直営)か外部委託か:施設内調理は温かい食事が提供でき、個別対応にも柔軟な傾向があります 。一方、外部委託は衛生管理が徹底されていますが、柔軟性に欠ける場合があります 。見学時にどちらの方式かを確認しましょう。
- 栄養士・管理栄養士の関与:施設に管理栄養士が常駐しているか、献立作成にどの程度関わっているかを確認しましょう。専門職が深く関わっている施設ほど、個々の健康状態に配慮した質の高い食事が期待できます。
チェックポイント2:献立の内容とバラエティを調べる
献立表からは、施設が食事の「楽しさ」をどれだけ重視しているかを読み取ることができます。
- 週間・月間献立表の確認:見学の際に、実際の献立表を見せてもらいましょう。メニューのマンネリ化を防ぐ工夫があるか、和洋中などバリエーションは豊かか、旬の食材が使われているかなどをチェックします。
- 行事食やイベント食の頻度と内容:お正月やクリスマスなどの年中行事に合わせた「行事食」や、その土地の「郷土料理」などを提供しているかどうかも大切なポイントです。特別な食事は、日々の生活に彩りと潤いを与えてくれます。
- 選択食(セレクトメニュー)の有無:週に一度でも、メインのおかずなどを自分で選べる「セレクト食」があると、入居者の満足度は大きく向上します。「自分で選ぶ」という行為が、食事への意欲を高めます。
チェックポイント3:見学・試食で五感で確かめる
施設選びで最も重要なのが、見学と試食です。資料だけではわからない、リアルな情報を五感で感じ取りましょう。
- 必ず試食を申し込む:多くの施設では、事前に予約すれば昼食などを試食できます。味付け、温度、硬さ、量などを実際に体験し、ご本人の好みに合うかを確認してください。費用だけで判断しないことが重要です。
- 食事中のダイニングの雰囲気を確認:試食の際には、食堂全体の雰囲気も観察しましょう。明るく清潔か、他の入居者は楽しそうに食事をしているか、スタッフは入居者にどのように接しているかなど、食事環境は満足度に大きく影響します。
チェックポイント4:個別対応の柔軟性を質問する
入居時は健康でも、将来的に身体状況が変化する可能性は誰にでもあります。将来を見据えて、個別対応の柔軟性を確認しておくことが安心につながります。
- 契約書・重要事項説明書を確認:契約を結ぶ前に、食事に関する項目をしっかり読み込みましょう。食費の内訳や、欠食した場合の返金ルール、特別な食事への対応などが記載されています。
- 具体的な質問をする:見学や契約の際に、将来起こりうる状況を想定して、具体的な質問を投げかけてみましょう。
- 「将来、飲み込みが悪くなった場合、きざみ食やソフト食にどの程度柔軟に対応してもらえますか?」
- 「アレルギーや苦手な食材がある場合、代替食の提供は可能ですか?」
- 「医師から減塩の指示が出た場合、すぐに対応してもらえますか?」
これらの質問に対する回答の丁寧さや具体性から、施設の対応力や姿勢を判断できます。
| カテゴリ | チェック項目 | 確認内容 |
| 味・品質 | 味付けは本人に合いそうか? | 薄すぎないか、濃すぎないか、出汁の風味はどうか |
| 食材の硬さは適切か? | 高齢者が食べやすいように調理されているか | |
| 温かいものは温かいか? | 配膳時の温度管理は徹底されているか | |
| メニュー | 献立にバラエティはあるか? | 季節感、行事食、選択食の有無 |
| 栄養バランスは考慮されているか? | 管理栄養士の関与、主食・主菜・副菜のバランス | |
| 個別対応 | 食事形態の変更は可能か? | きざみ食、ミキサー食などへの対応範囲と追加料金の有無 |
| 治療食への対応は可能か? | 減塩食、糖尿病食などの実績 | |
| アレルギー・苦手な食材への配慮はあるか? | 代替食の提供など、具体的な対応方法 | |
| 環境 | 食堂の雰囲気は良いか? | 明るさ、清潔さ、騒がしさ、席の配置 |
| スタッフの介助は丁寧か? | 食事中の声かけ、本人のペースに合わせているか | |
| 他の入居者は食事を楽しんでいるか? | 表情や会話の様子から満足度を推測する |
食事の未来:介護食を革新する最新テクノロジー
介護現場における食事の課題を解決するため、新しい技術の開発も進んでいます。これらのテクノロジーは、未来の介護食をより豊かで楽しいものに変える可能性を秘めています。
3Dフードプリンター
食材をペースト状にし、3Dプリンターで元の形そっくりに出力する技術です 。ミキサー食のように飲み込みやすく、かつ見た目は普通の食事と変わらないため、食欲を維持する効果が期待されています 。
栄養素をデータで管理し、一人ひとりに最適な栄養バランスの食事を「印刷」することも可能になります。これにより、画一的な集団調理と、個別対応という相反する課題を両立させる道が開かれます。
食事支援ロボット
AIカメラが搭載されたロボットアームが、利用者の口元や皿の上の食べ物を認識します。「唐揚げが食べたい」と声で指示すると、ロボットが自動的に唐揚げをすくって口元まで運んでくれます 。手が不自由な方でも、自分の意志で、自分のペースで食事をすることが可能になり、「自分で食べる」という尊厳を守ります。
新調理システム(真空調理法)
一部の先進的な施設では、「真空調理法」などの新しい調理技術が導入されています 。食材と調味料を真空パックして低温でじっくり加熱することで、少ない塩分でも味がしっかり染み込み、素材本来の風味を活かした、軟らかくおいしい料理を作ることができます 。これは、健康上の理由から薄味にせざるを得ない施設の食事と、濃い味を好む高齢者の味覚とのギャップを埋める画期的な解決策となり得ます。
まとめ:ご家族の働きかけが、「食べる喜び」を取り戻す一番の力になります
施設の食事が合わないという問題は、高齢者ご本人にとって、そしてご家族にとっても、非常につらく、根深い悩みです。しかし、その原因は一つではなく、解決策も一つではありません。
本記事で解説したように、まずは問題の根本原因がどこにあるのかを冷静に見極めることが大切です。それは、施設の味付けかもしれませんし、ご本人の身体的な変化や心理的な要因かもしれません。原因を正しく理解した上で、施設スタッフと協力し、一つひとつ解決策を試していくことが重要です。
食事の問題解決に向けた4つのステップ
- 正確に把握する:本人の話を聞き、様子を観察して具体的な状況を掴む。
- 具体的に相談する:感情的にならず、客観的な事実を基に施設と対話する。
- 選択肢を知る:食事形態の変更から外部サービスの利用まで、様々な解決策を検討する。
- 予防が最善:これから施設を選ぶ方は、食事を最優先事項の一つとして見学・試食を行う。
ご家族がご本人の一番の理解者となり、代弁者として施設に働きかけること。それが、ご本人が再び「食べることは楽しい」と感じられる日々を取り戻すための、最も大きな力になります。
「人手不足」や「コスト」など、施設のお食事に関するお悩みはありませんか?
「調理スタッフの応募が全く来ない」
「急な欠勤が出るたびに、現場がパニックになる」
「委託費や食材費の値上げで、食事部門が赤字だ」
少子高齢化が進む今、専門職の採用難やコスト高騰は、どの施設様でも避けられない課題です。 「今のスタッフだけで、なんとか食事提供を維持しなければならない」 そんなギリギリの状況で戦っていませんか?
その課題は、「人のスキルに頼らない仕組み」を導入すれば解決します。 東証スタンダード上場企業が提供する「こだわりシェフ」は、まさにそのための切り札です。
採用不要: 「湯煎・解凍」だけなので、誰でも均一に提供可能。
コスト削減: 専門職の人件費や食材ロスをカットし、経営負担を軽減。
味も保証: プロの料理人と管理栄養士が監修した「確かな味」。
「本当に素人でも回せるの?」「コストに見合う味なの?」 その判断材料として、まずは無料サンプルで「調理の手軽さ」と「味」を体験してください。
既存会員の方以外なら、どなたでもお申し込みいただけます。
導入を強制することは一切ありません。「万が一の時の備え」として試しておくだけでも価値があります。
まずはリスクのない無料サンプルで、その「手軽さ」と「味」を体感してください。



